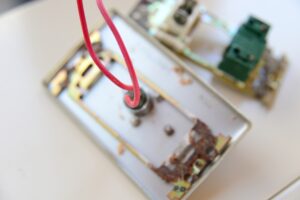| 職業/業務内容 | 現場監督 |
|---|---|
| 症状 | 胸痛・息切れ・たん・せき 、胸膜プラーク |
| 現在の状況 | 存命 |
| 年齢 | 80代 |
| 勤務形態 | 労働者 |
| ばく露時期 | 昭和42年(1967年)~平成18年(2006年) |
| ばく露年数 | 約40年 |
| ばく露した状況 | 建設現場において、現場監督としてアスベスト吹き付け後の検査や、床に飛散したアスベストを含む資材の清掃作業、アスベスト含有建材の加工作業の監督、解体現場の監督に従事し、アスベストにばく露した。 |
| 申請をお勧めした給付金制度 | ①労災保険 ③建設アスベスト給付金制度 |
| ご相談者 | 被災者本人 |
①ご相談内容
ご相談者様が長い間、現場監督として建設現場で仕事に従事していましたが、同僚が3名亡くなったことをきっかけに被災者も病院で診断を受けたところ、肺の胸膜プラークを指摘されたとのことでした。その後厚生労働省のホームページで建設アスベスト給付金の制度があると知り、弊所へ問い合わせをいただきました。
②弁護士からのアドバイス
1.アスベスト被害者の救済制度のご説明
アスベスト被害者を救済する制度には、大きく分けて3つの制度があることを説明しました。①労災保険、②石綿健康被害救済制度、③建設アスベスト被害救済制度です。
①に関しては、労働者または労災保険の特別加入者の方が対象です。
②に関しては、労働者かどうかなどを問わず、アスベスト関連疾患の患者を広く対象とした救済制度です。
③に関しては、労働者・一人親方・一定規模以下の事業主または法人代表者の方が対象です。
各制度の詳細につきましては、以下のコラムをご覧ください。
今回のご相談者様は胸部CTスキャンの画像をお持ちでしたので、そちらの画像を拝見したところ、肺を輪切りにしたCTにおいて肋骨と肋骨の間に白い石灰化が見られ、胸膜プラークが形成されておりました。
胸膜プラークはアスベストばく露がなければ形成されないとされており、アスベストばく露の明確な医学的証拠となるので、このCT画像より相談者様がアスベストを吸引していたことは明らかであること及びアスベスト給付金の認定において有利であることを判断できました。
胸膜プラークについて、以下のコラムもご参照ください。
2.まずは労災保険の認定を目指す
今回のご相談者様は労働者であったため、前述している①~③すべての制度が利用可能なことを説明し、また、相談者様がお持ちだった石綿健康管理手帳にも胸膜プラーク(石灰化あり)との所見の記載があったこと及び胸痛・息切れ・たん・せきの症状から石綿肺またはびまん性胸膜肥厚が発症しているか今後発症する可能性が高いことから、労災認定される可能性が十分にあることを重ねて説明しました。しかし、①と②の制度は併用することが不可能なので、より多くの給付金を獲得できる①労災保険と③建設アスベスト救済制度の申請をアドバイスしました。
所感・まとめ
アスベスト給付金制度は、とても複雑であり、「自分がどの制度をどの順番で利用すればよいのかわからない。申請方法もわからない。」という方がたくさんらっしゃいます。
今回のご相談者様には上記のようなアドバイスをしたところ、自身で申請を進めていくのに不安があるとのことでしたので、当事務所にご依頼いただく運びとなりました。
アスベスト被害に遭われた方、アスベスト被害でお亡くなりになったご家族の方は、早い段階でアスベスト給付金申請の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
この記事の監修弁護士

弁護士法人シーライト 副代表弁護士
小林 玲生起
神奈川県弁護士会所属。藤沢生まれ、藤沢育ち。アスベスト給付金申請の代理業務については弁護士向け教材の講師を務めるなど、詳しい知識を持つ。

弁護士法人シーライト 副代表弁護士
小林 玲生起
神奈川県弁護士会所属。藤沢生まれ、藤沢育ち。アスベスト給付金申請の代理業務については弁護士向け教材の講師を務めるなど、詳しい知識を持つ。